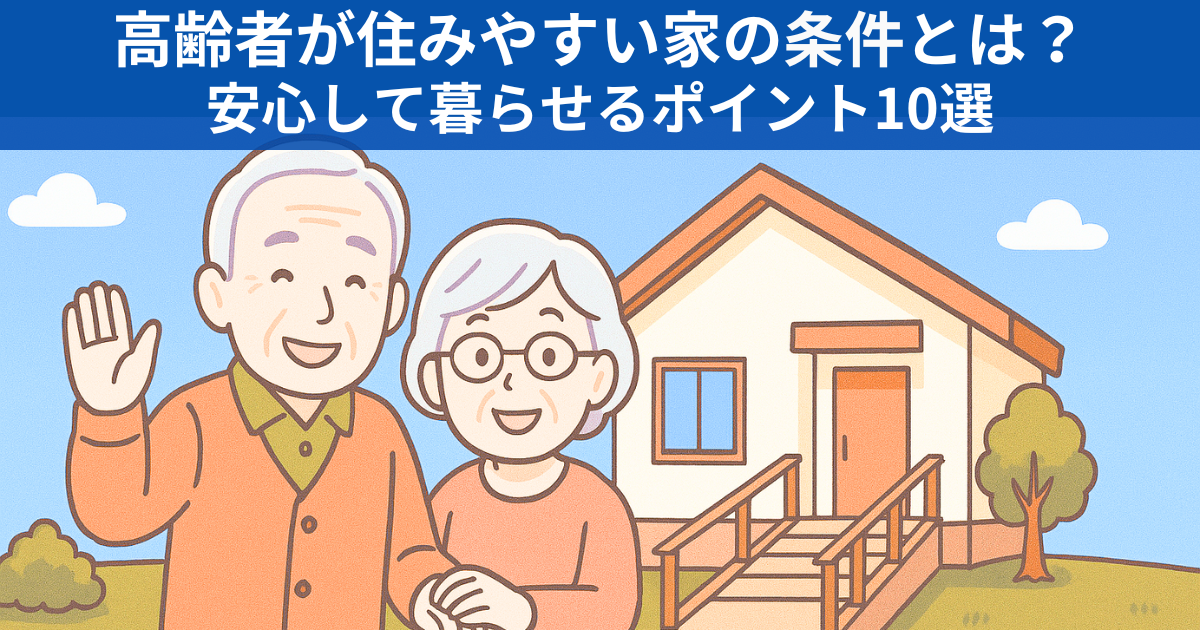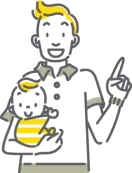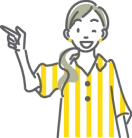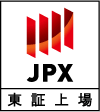人生においては、ライフステージが変わると、必要な住まいの条件も大きく変わります。
子育て中は広いリビングや庭、学校へのアクセスなど家族優先の間取りや環境が大切です。しかし、子どもが独立すると家に空き部屋が増え、年齢が上がるごとに段差や階段が負担になるなど、異なる視点から住まいを考える必要が出てきます。
そのため、ある程度年齢を重ねたタイミングで、より快適な環境を求めて住み替えを検討する必要がありますが、選び方を誤るとかえって不便を感じるケースも少なくありません。
購入後に後悔しないためにも、高齢者が安心して暮らせる家の条件を事前にチェックしておきましょう。
もくじ
高齢者が住みやすい家のポイント10選
高齢になると、足腰の衰えや視力の低下、持病の悪化などにより、日常生活を営むうえで様々な配慮が必要です。
そのため、高齢者が暮らす家を検討する際は、バリアフリー仕様や適切な動線計画といった、高齢者の生活スタイルに合わせることで、体への負担を減らし、安全に過ごしやすい環境を整えられます。
高齢者が住みやすい家のポイントは、以下のとおりです。
- バリアフリー設計
- クッション性が高く滑りにくいフロア材
- 明るく均一な照明
- 暖かい脱衣室と浴室
- 広めのトイレと浴室レイアウト
- 短く動きやすい動線
- 目から腰の高さで取り出せる収納
- 緊急時の連絡設備
- プライバシーと家族交流を両立する間取り
- メンテナンスがしやすい設備
それぞれのポイントについて確認しておきましょう。
バリアフリー設計
高齢者が住みやすい家のポイントの一つが、バリアフリー設計です。
高齢になるにつれて筋力や視力の低下により、部屋や廊下の出入口にわずかな段差があるだけでも、足を引っかけて転倒するリスクが高まります。また、車椅子を使用する場合には、その段差が大きな障壁となり、日常的な移動が難しくなることも少なくありません。
バリアフリー設計にすることで、転倒のリスクを抑えるだけでなく、車椅子での移動もスムーズに行えるようになります。
バリアフリー設計には、次のような工夫があります。
- 室内の段差をなくしてフラットな床面にする
- 玄関の出入口は階段ではなくスロープを設置する
- 扉を引き戸にする
- 廊下は車椅子が通れる幅を確保する
高齢になるほど足腰への負担が増えるため、バリアフリーの対応は早めの検討が大切です。ハウスメーカーの多くも、バリアフリーに配慮した家づくりを行っているので、将来を見据えた暮らしやすい住環境を整えましょう。
クッション性が高く滑りにくいフロア材
クッション性が高く滑りにくいフロア材の採用も高齢者が住みやすい家にするためのポイントです。
高齢者は筋力やバランス感覚が低下しており、ちょっとした段差や滑りやすい床で転倒するリスクがあります。転倒すると骨折などの大きな怪我につながることも多く、日常生活に大きな影響を及ぼしかねません。
クッション性が高く滑りにくいフロア材を採用することで、転倒のリスクを軽減できます。また、衝撃を吸収するため、万が一転倒しても怪我のリスクを抑えられます。
以下は、クッション性の高いフロア材を比較した表です。施工方法や主な特徴をまとめてあるので、好みに合ったものを選ぶ際の参考にしてみてください。
| 床材 | クッション性 | 施工方法 | 主な特長 |
|---|---|---|---|
| タイルカーペット | 厚みがあり衝撃を吸収しやすい | 裏面が吸着加工されているタイプは敷くだけ | 滑りにくく足腰への負担を軽減できるうえ、部分洗いにも対応しやすい |
| コルクタイル | 天然素材の適度な弾力があり、足腰への負担を軽減 | 専用接着剤で貼るタイプや、はめ込み式のものがある | 保温・防音性が高くDIYでの施工もしやすい |
| クッションフロア | 適度な厚みで衝撃を緩和する | 接着剤または両面テープで簡易施工が可能 | 水拭きやモップ掃除ができ、豊富な柄から選べる |
| 発泡層クッションフロア | 通常のクッションフロアより厚みがあり衝撃吸収性が高い | 接着剤または両面テープで施工 | 転倒時のダメージを和らげ、汚れの拭き取りが簡単 |
| 発泡層の長尺シート | クッション性が高く歩行時や転倒時の衝撃を吸収 | 基本は接着剤で貼る(重量があるためズレにくい) | 医療施設などでも使用されるほど耐久性があり抗菌機能も充実 |
リビングやダイニング、寝室といった日常的に過ごす時間が長い場所だけでなく、玄関や洗面室、階段などの転倒リスクが高い場所にも使用することで、安全性が高まり安心して暮らせます。
明るく均一な照明
高齢者が住みやすい家は、照明も大切な要素です。
年齢を重ねるにつれて視力が低下しやすく、室内が薄暗いと必要な物が見つからないことや、家具にぶつかってしまうリスクが高まるためです。
とりわけ上の棚など高い位置の物を取ろうとする際は手元が見えにくく、落としてケガをする場合もあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、住まい全体を明るく均一に照らす照明計画が欠かせません。
また、室内の照明は、生活が不便になるだけでなく転倒のリスクも高まります。
特に、階段や廊下、トイレ、浴室などは、十分な明るさが確保されていないと、大怪我につながる可能性があるため注意が必要です。
そのため、「おしゃれな雰囲気を演出するために間接照明をメインにしたい」「重厚感を出すために室内をあえて薄暗くしたい」といった考えがあったとしても、高齢になったときのことを考えるとおすすめできません。
安全性や快適性を考慮して視認性の高い照明を採用し、十分な明るさを確保することが大切です。
暖かい脱衣室と浴室
高齢者が住みやすい家を考えるうえで、忘れてはいけないのが脱衣室と浴室を暖かく保つ工夫です。
人間の体は、急激な寒暖差が生じると温度変化に合わせて血圧が急激に変動し、心臓や血管に大きな負担がかかります。これがいわゆる「ヒートショック」と呼ばれる現象で、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な健康被害を引き起こす原因になっています。特に、高齢者の場合は以下の理由から、ヒートショックのリスクが高くなりがちです。
- 血管の弾力性が低下し、温度変化による血圧の変動をコントロールしにくくなる
- 自律神経の反応速度が遅くなり、温度変化に対する体の適応が遅れる
- 温度変化に対する感覚が鈍くなり、危険な状態に気づきにくくなる
ヒートショックを抑えるには、次のような住宅設備を取り入れるのが効果的です。
断熱性・気密性を高める
高気密高断熱住宅では、気密性と断熱性能によって温度変化が生じにくいため、ヒートショックの原因となる室内の温度差が抑えられます。
また、冬場は外の冷気を遮断し、夏場は外の熱気を抑えられるため、空調効率が良くなり光熱費の削減も期待できます。
全館空調の導入
全館空調とは、家中にダクトなどを巡らせて空気を循環させ、室内の温度や湿度を一定に保つシステムです。通常のエアコンは部屋ごとに設置されますが、全館空調は一つの装置で建物全体をコントロールします。
廊下や脱衣所などの細かい空間に至るまで温度差を抑えられるため、脱衣所やトイレなどが寒くなるのを防ぎ、ヒートショックのリスクを軽減できます。
部屋ごとに暖房器具を設置しなくて済むため、空間をすっきり使えるのもメリットです。
浴室換気暖房乾燥機の活用
ヒートショックのリスクを抑えるには、浴室換気暖房乾燥機の導入も効果的です。
これは換気・暖房・乾燥を一度に行える装置で、入浴前にあらかじめ浴室や脱衣所を温めておけば、入浴時の寒暖差を抑えられます。
機種によっては予約機能や温度変化を知らせるアラーム機能、脱衣所まで暖める機能なども選べるため、入浴習慣に合わせて最適なタイプを導入しましょう。
広めのトイレと浴室レイアウト
将来的に車椅子を使用したり、介助が必要になったりすることを考えると、トイレや浴室に十分なスペースを確保しておくことがとても大切です。
空間が狭いと、入室や移動に時間がかかるうえ、介助者がスムーズにサポートしづらくなり、日常生活が不便になる可能性があるためです。
そのため、トイレや浴室のドア幅や廊下の幅を広めに設計しておくことで、車椅子や介助が必要な場合でもスムーズに移動できるようになります。事前に十分なスペースを確保しておけば、万が一の時も安全で快適に過ごせる住まいを実現できるでしょう。
短く動きやすい動線
高齢になって体力が落ちてくると、家の中を移動するだけでも負担が増してきます。
そのため、家事や日常生活をスムーズにこなすためには、できるだけ短く移動できる動線を確保しておくことが大切です。
キッチンやリビング、洗面室、浴室、寝室など、頻繁に使う部屋を近い場所にまとめて配置すれば、移動距離が減って足腰への負担だけでなくストレスも大幅に軽減できます。
また、転倒などのリスクも抑えられるので安心です。
今はまだ体力に自信があっても、将来の生活を考えて動線を重視した設計を心掛けると、年齢を重ねても快適な暮らしを続けられるでしょう。
目から腰の高さで取り出せる収納
高齢者が住みやすい家を考える際、収納の配置は大切なポイントです。
年齢が上がるにつれ、筋力やバランス力が低下しやすくなり、荷物を取るときに腰をかがめるだけでも大きな負担になるためです。
また、目より高い位置にある収納から荷物を下ろそうとして椅子に乗ると、転倒などのリスクが増し、荷物を落としてしまう可能性もあります。
一方、目の高さから腰の高さに収納を設置しておけば、立ったままで必要な物を簡単に取り出せます。探しものをする際にも無理な姿勢を取る必要がないため、身体への負担が軽減できるのです。楽な姿勢で収納の中を確認したり、出し入れしたりできることで、日常生活をより快適に過ごせるようになるでしょう。
緊急時の連絡設備
万が一のトラブルが起きた際に、すぐに助けを求められる環境を整えておくことは、高齢者が住む上で大きな安心につながります。年齢を重ねると、急な体調不良や転倒、事故、不審者の侵入など、さまざまなリスクが高まるためです。
緊急時に素早く連絡を取れる手段を用意しておけば、いざというときに迅速な対応が可能です。
たとえば、リビングや寝室、トイレ、浴室など頻繁に利用する場所に緊急呼び出しボタンを設置しておけば、異変があった際に即座に助けを求められます。
また、見守りセンサーやカメラを設置して、異常を検知すると家族に自動で通知される仕組みを導入すれば、離れて暮らしていても迅速な対応が可能です。どこにいても家族や介助者との連絡をスムーズに行える環境を整えることで、高齢者の暮らしは格段に安全で安心なものになります。
プライバシーと家族交流を両立する間取り
高齢者が住みやすい家を考える際、家族同士の交流を大切にしつつ、それぞれがリラックスできるプライベート空間を確保することが重要です。ゆったりと集まれる共有スペースと、自分の時間を過ごせる個室をバランスよく配置することで、高齢者も家族も安心して暮らせる理想の住まいを実現できます。
家づくりやリフォームを計画する際は、「プライバシー」と「家族交流」の両面を意識して間取りを検討してみましょう。
夫婦それぞれに個室を用意する
同じ家で暮らしていても、それぞれが静かに過ごせる部屋を持っておくと、自分の趣味を楽しんだり、休息を取ったりする際に気兼ねなく過ごせます。特に高齢になると、長時間一緒に過ごすより、適度な距離感があるほうがストレスを軽減できるケースも少なくありません。
LDK(リビング・ダイニング・キッチン)の中心化
リビングやダイニング、キッチンを一体化させて広々とした空間にすることで、家族同士が自然と集まりやすくなります。食事や会話を共有できる「集いの場」が中心にあると、コミュニケーションの機会が増えて家族間のつながりが深まりやすくなるでしょう。
適切な動線と仕切りの配置
家族が集まるスペースと個室をほどよい距離に配置することで、必要に応じてプライベート空間に戻りやすくなります。また、引き戸やスクリーンパーティションなどを使い、簡単に開閉や区切りができるようにしておくと、気軽にプライバシーを確保したり、開放して交流を促進したりと柔軟に空間を使い分けることが可能です。
メンテナンスがしやすい設備
高齢者が住みやすい家にするには、日常の手入れや定期的な修繕が無理なく続けられるよう、メンテナンスのしやすい設備を選ぶことが大切です。
どんなに便利な機能があっても、維持管理が大変だと使いこなすのが難しくなったり、部品交換などで高額な費用がかかったりして大きな負担になる可能性があります。
そこで、汚れが付きにくい素材やシンプルな設計のもの、頻繁なメンテナンスが不要な設備を選ぶと安心です。
また、メーカーの保証内容やアフターサービスの充実度を確かめておけば、万が一のトラブルが起きた際もスムーズに対応できます。室内の設備だけでなく、外壁や屋根など建物全体の耐久性やお手入れのしやすさも確認しておくと、将来的な負担を軽減しながら長く快適に暮らせる住まいを実現できるでしょう。
失敗しないための3つのポイント
高齢者が住みやすい家づくりで失敗しないためのポイントは、以下の3つです。
- 実績の豊富なハウスメーカーに依頼をする
- 無理な資金計画を立てない
- 必ず複数のハウスメーカーを比較する
これらを意識することで、家づくりや資金面の失敗を防ぎやすくなります。
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
実績の豊富なハウスメーカーに依頼をする
高齢者が住みやすい家を建てるには、細かな部分まで配慮しなければなりません。
経験豊富なハウスメーカーは、これらのバリアフリー・ユニバーサルデザインに関する要件を整理しながら設計・施工を進める専門的なノウハウを持っています。
具体的には、地元自治体が提供する補助金・助成制度の利用方法や、車椅子使用者や介護者のための動線設計基準といった実務的なポイントを熟知していることが多いです。また、将来的に介護リフォームが必要になった際も、あらかじめ強度計算や配管・配線の取り回しを考慮しておくことで、負担を最小限に抑えたリフォームを実現できます。
「バリアフリー」とひと口に言っても、生活スタイルや健康状態、家族構成などに応じて必要な仕様は異なります。実績豊富なハウスメーカーなら、数多くの施工事例から培った知見を基に、個々の状況に合ったアドバイスやプランの提案をしてくれるため、高齢者が安心して暮らせる住まいを実現しやすくなるのです。
ハウスメーカーを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- 高齢者向け住宅の施工実績が豊富か
- 口コミや評判が良いか
- 長期保証やアフターサービスが充実しているか
- いつでも相談できる体制が整っているか
- 過去の施工事例を確認できるか
施工実績や保証・アフターサービス、過去の施工事例などは、ハウスメーカーが自社の魅力を伝えるための重要な情報です。そのため、公式サイトに掲載されていることが一般的です。
無理な資金計画を立てない
高齢者が住みやすい家づくりで失敗しないためのポイントの一つが、無理な資金計画を立てないことです。
住居費の負担が大きくなりすぎると、家計が圧迫され、生活に余裕がなくなる可能性があります。
さらに、老後資金や医療費、子どもの教育費など、将来的に必要なお金を確保するのが難しくなることも考えられます。そのため、将来の生活を見据えた資金計画を立てることが大事です。
例えば、住宅ローンを利用する場合、現在の収入だけを基準に借入額を決めると、定年後に収入が減った際に返済が厳しくなる可能性があります。
定年後の収入減も考慮した無理のない借入額や返済プランを設定することが重要です。
また、自治体によっては高齢者向け住宅の設備設置や改修に対する補助金制度があるため、事前に確認しておきましょう。
資金計画を立てる際は、初期費用だけでなく、維持管理にかかるランニングコストも考慮する必要があります。ランニングコストはハウスメーカーの保証やアフターサービスの内容によって変わるため、契約前にしっかり確認しておくことが大切です。
家を建てる際、気持ちが高ぶって予算を超える仕様や設備を希望することがありますが、将来の生活に影響を与える可能性があるため、無理のない資金計画を立てましょう。
必ず複数のハウスメーカーを比較する
高齢者が住みやすい家づくりで失敗しないために、必ず複数のハウスメーカーを比較することが大切です。
数多くのハウスメーカーが存在しており、それぞれで特徴や強みが異なるためです。複数のメーカーを比較することで、最も条件が良く信頼できるハウスメーカーに依頼できます。
もし比較せずに最初から一社に決めてしまうと、もっと条件の良いハウスメーカーや、高齢者向け住宅の実績が豊富なメーカーを見逃すことになるかもしれません。
家づくりは高額な資金が必要となるため、後悔を避けるためにも、慎重にプロセスを進めることが大事です。
複数のハウスメーカーを比較する際には、上場企業のリビン・テクノロジーズが提供する無料サービス「家づくりプラン」がおすすめです。無料で利用でき、ハウスメーカーや工務店に一括で間取りプランや資金計画の作成を依頼できます。
複数のメーカーから提案を受け、その内容や対応を比較して、自分たちの条件に最適なメーカーを選ぶことが可能です。また、一社ずつ個別に問い合わせる手間を省けるため、効率よく比較ができます。
「家づくりプラン」を利用して、条件が良く信頼できるハウスメーカーを見つけましょう。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なく、住宅メーカーを比較検討していただくことが可能 です。 土地から探す、実家を建て替えるなど、あなただけの家づくりプラン作成をお手伝いします。 また、注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。 注文住宅でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご利用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)