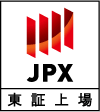プロパンガス(LP)は、都市ガスの供給が行き届かない地域や戸建住宅を中心に、今なお根強い需要があります。一方で、都市ガスに比べて料金が高くなりやすく、利用者にとって負担となっているのが現状です。
実際に、都市ガスと比較すると、プロパンガスの料金は平均で約6倍も高いというデータもあります。背景には、配送にかかるコストや契約の仕組み、さらには業界特有の価格設定など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
しかし近年では、法改正などの影響により料金体系の透明化が進みつつあり、これまでのように不透明で一方的な価格設定が見直され始めています。
また、利用者自身の行動によってプロパンガスの料金を抑えることも十分に可能です。
ここでは、プロパンガスの料金体系の基本的な仕組みから、料金が高くなる4つの具体的な理由、さらに家計の負担を軽減するために実践できる対策まで解説します。
もくじ
プロパンガス(LPガス)の料金体系
プロパンガスの料金は、「基本料金」と「従量単価」で構成されます。
基本料金は、ガスの使用量に関係なく毎月固定でかかる料金です。ガスメーターの設置や保安管理などの費用が含まれており、契約している限り必ず支払う必要があります。
また、従量料金(従量単価)は、実際に使用したガスの量に応じて計算される料金です。使用量が増えるほど料金も高くなります。
なお、基本料金や従量単価の金額は一律ではなく、契約しているガス会社や地域(都道府県)によって異なります。そのため、同じ使用量でも住んでいる地域によって支払う金額に差が出ることがあります。
基本料金
プロパンガスの基本料金は、ガスの供給設備を安全に維持・管理するための固定費です。 たとえガスをまったく使用しなかった月でも、基本料金は変わらず発生します。
この料金には、以下のような保安管理や設備維持にかかる費用が含まれています。
| 基本料金に含まれる主な内容 | 具体的な作業内容 |
|---|---|
| ガス容器の管理 | ガスボンベの配送・交換 |
| 使用状況の確認 | 月1回の検針(使用量の確認) |
| 安全対策 | ガスメーターや配管などの定期保安点検 |
| 設備対応 | 部品交換やトラブル対応 |
輸入コストや、ガス会社の人件費は地域によって差があるため、基本料金もそれに伴い変わります。
また、地域別だけではなく、燃料価格の変動などによっても基本料金は変わりますが、平均価格はおよそ1,900円程度です。数百円の誤差ならば許容範囲内ですが、基本料金が2,500円を超えているようなら、相場よりも高いと見てよいでしょう。
基本料金が相場よりも高くなる主な要因は、ガスの配送コストが高い地域(山間部や離島など)での人件費や輸送費の増加、競争が少ないエリアでの強気な価格設定などが挙げられます。
加えて、保安管理や設備サービスの上乗せ、長年契約を見直していないことによる割高な料金の継続も要因となります。
従量単価
従量単価とは、使用したガスの量に応じて料金が変動する「従量料金」の単価部分のことです。従量単価に、実際のガス使用量をかけた金額が「従量料金」として請求されます。
従量単価の決め方には、以下3つのタイプがあります。
- スライド型
- 原材料調整型
- 固定型
スライド型は、使用量が増えるにしたがって単価が安くなる料金設定です。そのため、一般家庭よりもガスを多く使用する家庭や店舗ではコストを抑えやすいのが特徴です。
また、原材料調整型は、LPガスの原材料費(主に輸入価格)が変動すると、それに応じて単価も変わる仕組みです。価格見直しの頻度や反映のタイミングはガス会社ごとに異なります。
固定型は一定期間、単価が固定されるタイプです。原料価格や使用量に関わらず料金が変動しないため、毎月のガス代の見通しが立てやすいというメリットがあります。固定期間の長さはガス会社によって異なります。
従量単価のタイプは、世帯の利用状況によって変わります。例えば、家族が多くてガスの使用量が多い家庭なら「スライド型」を選ぶと節約につながります。
一方で、使用量が少ない家庭や、毎月のガス代を安定させたい場合は「固定型」の方が向いています。このように、自分のライフスタイルや使用傾向に合った料金タイプを選ぶことで、ムダな支出を抑えたり、家計管理をしやすくしたりできるのです。
料金相場は都市ガスの6倍
一般的に「都市ガスよりもプロパンガスの方が高い」と言われますが、実際にはどのくらい差があるのでしょうか。全国平均で比較すると、都市ガスの5㎥あたりの料金は939.8円に対し、プロパンガスは5,610円となっており、約6倍も高いという結果になっています。
参考:
ガス平均単価の推移|新電力ネット
一般小売価格 LP(プロパン)ガス 確報(偶数月調査)|一般財団法人 日本エネルギー経済研究所
さらに、プロパンガスは都市ガスと異なり、地域や契約しているガス会社によって料金に大きな差があるのが特徴です。
公表する価格は基本料金および消費税込みの価格です。(単位:円)
2024年12月 基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3 北海道 2,217 6,821 11,187 19,487 42,875 北海道局 2,217 6,821 11,187 19,487 42,875 青森県 2,090 6,415 10,879 19,419 44,621 岩手県 2,102 6,295 10,460 18,241 39,583 宮城県 1,934 5,571 9,213 16,086 35,098 秋田県 2,023 6,065 10,045 17,478 38,380 山形県 2,060 6,112 10,251 18,175 39,969 福島県 1,971 5,718 9,431 16,482 36,000 東北局 2,018 5,971 9,938 17,451 38,455 茨城県 1,842 5,187 8,532 14,932 32,978 栃木県 1,803 5,161 8,522 14,889 32,740 群馬県 1,887 5,161 8,433 14,711 31,893 埼玉県 1,904 5,115 8,366 14,806 33,186 千葉県 1,866 5,133 8,379 14,656 32,453 東京都 1,893 5,062 8,266 14,556 32,369 (除伊豆諸島) 1,895 5,029 8,207 14,412 32,002 神奈川県 1,935 5,261 8,592 15,072 33,726 新潟県 2,109 5,797 9,453 16,504 36,213 (除佐渡) 2,133 5,738 9,287 16,151 35,186 長野県 1,918 5,567 9,108 15,817 34,569 山梨県 1,834 5,134 8,426 14,806 32,743 静岡県 1,908 5,485 8,911 15,497 34,044 関東局 1,899 5,266 8,616 15,085 33,330 除伊豆諸島・佐渡 1,898 5,255 8,593 15,038 33,208 愛知県 1,905 5,418 8,801 15,213 32,954 岐阜県 1,938 5,559 9,018 15,820 34,510 三重県 1,922 5,441 8,750 15,030 32,165 富山県 2,198 6,166 9,989 17,146 35,496 石川県 2,034 5,857 9,604 16,615 36,005 中部局 1,973 5,614 9,107 15,764 33,891 福井県 1,954 5,775 9,391 16,230 34,869 滋賀県 2,030 5,496 8,883 15,316 32,667 京都府 1,998 5,507 8,926 15,487 33,765 奈良県 1,936 5,226 8,441 14,559 31,777 大阪府 1,849 5,208 8,491 14,806 32,542 兵庫県 2,139 5,774 9,246 15,678 33,803 和歌山県 2,016 5,364 8,571 14,545 31,544 近畿局 1,993 5,494 8,871 15,255 33,070 鳥取県 2,104 6,089 9,908 17,264 37,192 島根県 2,179 6,280 10,262 17,880 39,381 除隠岐 2,177 6,314 10,334 18,024 39,729 岡山県 2,072 5,848 9,484 16,270 34,896 広島県 2,026 5,830 9,182 15,545 33,139 山口県 2,143 6,125 9,903 16,928 36,377 中国局 2,093 5,993 9,658 16,580 35,667 中国局除隠岐 2,091 5,994 9,662 16,586 35,678 徳島県 2,120 5,519 8,868 15,153 32,639 香川県 2,058 5,683 9,247 16,001 34,943 愛媛県 2,019 5,559 9,047 15,535 33,496 高知県 2,057 5,442 8,699 14,761 31,230 四国局 2,062 5,555 8,981 15,399 33,187 福岡県 2,058 5,600 8,968 15,102 31,409 佐賀県 2,045 5,856 9,419 15,890 33,263 長崎県 1,895 5,595 9,123 15,768 33,723 除対馬五島 1,859 5,500 8,941 15,355 32,166 熊本県 1,837 5,422 8,778 14,811 30,561 大分県 1,907 5,424 8,798 15,075 32,455 宮崎県 1,944 5,609 9,256 15,963 33,444 鹿児島県 1,762 5,600 9,191 15,769 34,169 除奄美熊毛 1,721 5,538 9,068 15,437 33,000 九州局 1,922 5,572 9,039 15,397 32,489 除離島 1,918 5,550 8,992 15,277 32,052 沖縄県 1,836 5,594 9,325 16,298 36,144 除宮古八重山等 1,861 5,644 9,387 16,339 36,004 沖縄総合事務局 1,836 5,594 9,325 16,298 36,144 除宮古八重山等 1,861 5,644 9,387 16,339 36,004 全国 5,610 9,154 15,880 34,532 除離島 5,606 9,145 15,857 34,457
北海道や東北、中国地方では全国平均よりも約1,000円近く高い水準となっており、地域によっては5㎥あたりの料金が6,800円を超えるケースもあります。
プロパンガスの料金が高くなる4つの理由
プロパンガスの料金が都市ガスよりも高い理由は、以下のとおりです。
- ガスボンベの交換にコストがかかる
- 料金はガス会社が自由に設定
- ガス会社同士で料金を調整
- 無償賃与契約の設置費用が料金に上乗せされる
料金が高額となる主な理由4つについて、本章で詳しく解説します。
ガスボンベの交換にコストがかかる
プロパンガスの価格が高くなりやすい理由のひとつは、ガスボンベの交換や配送にかかるコストが上乗せされているためです。
都市ガスは地下のガス管を通じて各家庭に供給されるため、基本的に人手はかかりません。
一方で、プロパンガスは各家庭や建物にガスボンベを設置し、ガス管に接続して供給する仕組みです。ガスボンベが空になるとガスの供給が止まるため、定期的にボンベの交換が必要です。継続的な利用には、交換作業を行うスタッフの人件費や、ボンベを運搬するトラックのガソリン代・維持費などの輸送コストが発生します。
とくに、山間部や過疎地では配送に手間と時間がかかるため、こうしたコストはさらに高くなる傾向にあります。
このように、人件費や輸送費といった“目に見えないコスト”が料金に上乗せされるため、都市ガスと比べてプロパンガスはどうしても割高になりやすいのです。
料金はガス会社が自由に設定
プロパンガスは、ガス会社が料金を自由に設定できる「自由料金制」を採用しています。
都市ガスのように国や自治体の認可が必要な「公共料金」とは異なり、プロパンガスは各社が独自に料金を設定できるため、価格に大きなばらつきが出やすいのが特徴です。
そのため、同じ地域・同じ使用量であっても、契約しているガス会社によって月々の支払い額が大きく異なるケースも珍しくありません。
このように、プロパンガスは料金が不透明で相場が分かりづらいことから、高いと感じられる原因にもなっています。
無償貸与契約の設備費用が料金に上乗せされる
プロパンガスには「無償貸与契約」と呼ばれる仕組みがあり、それが料金を高くする原因のひとつになっています。
無償貸与契約は、ガス会社がガスの配管や設備の設置費用を一時的に無料で提供する代わりに、一定期間ガスを使ってもらうことを条件とする契約です。新築住宅やリフォームのタイミングでこの契約を利用すれば、初期費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、完全に「無償」というわけではありません。
実は、ガス会社は、設置や工事にかかった費用を毎月のガス料金に少しずつ上乗せするかたちで回収します。つまり、工事費用を分割で払っているようなものなのです。
また、上乗せされている金額は契約書や請求書に明記されないことが多く、実際には必要以上の費用が上乗せされているケースもあると言われています。
さらに注意が必要なのは、無償貸与契約には一定の契約期間が設けられている点です。
そのため、期間内に「ガス代が高いから他社に乗り換えたい」と思っても、簡単に解約できません。もし契約期間中に他社へ乗り換える場合は、残りの設備費用を一括で請求されることがあります。
法改正で料金の透明化・適正化が進んでいる
プロパンガスの料金が高い理由としては、人件費や配送コストの上乗せといった納得できる側面もあります。一方で、料金設定そのものが不透明だったことも否定できません。
こうした状況を改善し、消費者が不利益を被らないようにするために、2024年4月に「液化石油ガス法改正省令」が施行されました。
この法改正では、以下の3つの点が大きく見直されました。
- 過大な営業行為の制限
- ガス料金の事前の情報提供
- 三部料金制の徹底
それぞれの内容について、以下で詳しく解説します。
過大な営業行為の制限
1つ目の改正点は、ガス契約を結ばせるための過剰な営業行為の禁止です。
例えば、契約を取る目的で高額なプレゼントを提供する行為や、 「工事費用を無料にする代わりに2年間は契約継続が必須」といった条件付きの契約は、2024年4月以降すべて禁止されます。
これにより、消費者に不利益を与える営業手法が厳しく制限されます。
ガス料金の事前の情報提供
2つ目は、ガス料金を事前に開示する義務の導入です。
従来、特に賃貸物件ではガス料金が入居前に明示されていないケースが多く、「引っ越してから初めての請求額を見て驚く」といったトラブルが後を絶ちませんでした。
しかし、法改正により、賃貸物件の選定段階で、プロパンガスの料金情報もあわせて提示することが義務付けられました。入居者は事前にガス料金を確認したうえで物件を選べるため、料金に対する納得感が高まると期待されています。
三部料金制の徹底
三つ目の改正点は、三部料金制の徹底です。
従来のプロパンガスの料金体系は、基本料金と従量料金の二部構成でした。
二部構成では、設備のメンテナンス料金など設備費が不透明であり、過剰な設備費用を上乗せしているケースがあり、プロパンガスの費用が高額となる要因のひとつとなっていました。
改正によって、プロパンガスの料金は基本料金・従量費用・設備費用の三部構成となり、設備にかかる料金が透明化されます。
すでに契約を結んでいる住宅も二部制から2025年以降、順次三部料金制へと切り替わります。また、従来はWi-Fiやエアコンなど、プロパンガスとは無関係な設備の費用を料金に上乗せする業者も存在しましたが、改正によって禁止となりました。
さらに賃貸住宅向けのプロパンガス料金に、ガス器具など消耗品に関する設備の費用の計上も禁止行為です。
無関係な設備費用の上乗せ禁止と、賃貸住宅向けの消耗品設備費用の上乗せ禁止は、施工後に契約した住宅などに適用されますが、徐々にプロパンガスの料金は透明化され、納得のいく料金へと変化するでしょう。
プロパンガスの料金を抑える方法
2024年の法改正により、プロパンガスの料金体系は透明化が進み、今後新たに契約を結ぶ場合、過去のように不透明で高額な料金を請求されるリスクは少なくなると考えられます。
とはいえ、都市ガスと同じくらいまで料金が下がる保証はありません。
そのため、少しでもプロパンガスの負担を軽くしたい方は、自分自身で対策を講じることが大切です。
プロパンガスの料金を抑えるために有効とされる方法は、主に以下の3つです。
- 現在のプロパンガス会社に料金交渉をする
- 複数のガス会社を比較して切り替える
- プロパンガスから都市ガスへの切り替えを検討する
それぞれの方法について、以下で詳しく説明します。
現在のプロパンガス会社に料金交渉をする
プロパンガスの料金を抑えるための対策の一つが、現在契約しているガス会社に対しての料金交渉です。
プロパンガスは「自由料金制」が採用されているため、各ガス会社が料金を独自に設定しています。 つまり、交渉次第では料金の見直しが可能ということです。
ただし、根拠なく「安くしてほしい」と伝えるだけでは、交渉がうまく進まない可能性があります。あらかじめ、現在のガス料金と地域の相場を調べておき、データをもとに交渉するのが効果的です。
また、他社の方が安い料金で提供していることを具体的に伝えると、説得力が高まります。
ガス会社にとって、契約を解約されることは大きな損失につながるため、値下げに応じてくれる可能性は十分にあるでしょう。
複数のガス会社を比較する
交渉が苦手、または現在のガス会社に不信感がある場合は、他社への切り替えを前向きに検討してみましょう。
切り替え先は、複数のガス会社の料金を比較して選ぶことが大切です。
最近では、地域ごとの複数のガス会社から一括で見積もりを取得できる比較サイトも増えており、手軽に料金比較が可能です。
料金を比較したら、3社程度に絞り、実際に訪問見積もりを依頼しましょう。
見積もり時には、他社の料金を提示することで、契約前に値下げを引き出せるケースが多くなります。こうした価格競争が発生することで、通常よりも安い料金で契約できる可能性が高まります。
ただし、注意点もあります。
中には、「最初の1カ月だけ安く見せて、すぐに元の料金に戻す」といった悪質な例もあるのです。契約内容や料金の改定条件について、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
プロパンガスから都市ガスへの切り替え
もしお住まいの地域に都市ガスのインフラが整っている場合は、プロパンガスから都市ガスへの切り替えも選択肢の一つです。
都市ガスはプロパンガスに比べて料金が安いため、長期的には光熱費の節約につながる可能性があります。ただし、切り替えには初期費用がかかる点に注意が必要です。
都市ガスの導管を公道から自宅まで引き込むためには、距離に応じて費用が発生し、平均的には10万〜20万円程度が相場とされています。
正確な費用は立地条件によって異なるため、切り替えを検討する際は必ず事前に見積もりを取りましょう。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なく、住宅メーカーを比較検討していただくことが可能 です。 土地から探す、実家を建て替えるなど、あなただけの家づくりプラン作成をお手伝いします。 また、注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。 注文住宅でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご利用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)